
ふるさと納税を利用しているが、イマイチ仕組みがよく理解できないという方もいるでしょう。
ふるさと納税はある程度、仕組みを理解していないとお得に利用できていない可能性があります。
ふるさと納税をお得に利用する上で最も重要なポイントが控除限度額の把握。
限度額の把握が間違っていると自己負担額が大きくなってしまい、お得度が下がってしまいます。
そこで今回は、ふるさと納税の限度額の下記ポイントについて解説します。
- ふるさと納税の控除の仕組みとは?
- 控除限度額は年収一覧で確認できる?
- 控除限度額のシミュレーション方法
- 限度額を超えたら全額自己負担?対処法は?
ふるさと納税とは?控除の仕組みは?

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に寄附額のうち2,000円を越える部分(一定の上限あり)について、所得税からの控除(還付)と翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられる制度。
ふるさと納税をした額から自己負担額の2,000円を差し引いた部分が所得税の還付と翌年度の住民税の減額で戻ってくるイメージ。
実際の控除額の計算方法は下図の通り。
以下の図や計算式を暗記する必要はありませんが、大まかに控除の仕組みを知っておく事は重要でしょう。

(出典:総務省)
【①所得税からの控除】
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
【②住民税からの控除(基本分)】
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
【③住民税からの控除(特例分)】
(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)
上図の【③住民税からの控除(特例分)】は住民税所得割額の2割までなどと決まっています。
よって、【③住民税からの控除(特例分)】が住民税所得割額の2割を超える場合、(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えてしまします。
控除限度額は年収一覧で確認できる?

ふるさと納税の控除限度額の目安として総務省のHPなどに年収一覧が掲載されていることがありますが、一覧の限度額を参考にすると自己負担額が2000円を超えてしまう可能性があります。
その理由は、一覧の注釈部分にも書かれていますが、住宅ローン控除や医療費控除などが考慮されていないから。
住民税(所得割額・均等割額)の計算方法は下図の通り。

(出典:https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/inhabitant-tax-845)
上図の通り、税金は収入ではなく、課税所得に税率を掛けて計算します。
所得とは収入から必要経費や各種控除を引いたもの。
所得控除とは、住宅ローン控除や医療費控除など。
所得控除を考慮して徴収される予定の住民税額を正確に把握しないと、正しい控除限度額が分かりません。
年収一覧の限度額は、収入から住宅ローン控除などが差し引かれていないので、徴収される予定の住民税額が本来の額より高くなってしまいます。
よって、年収一覧を参考にしてふるさと納税を行うと、自己負担額が2000円よりも高くなる可能性があります。
控除限度額のシミュレーション方法

所得控除を考慮した控除限度額を計算するには、シミュレーションサイトを活用するのが便利です。
例えば、下記のようなサイトを利用するといいでしょう。
シミュレーションサイトを選ぶ際には、家族構成や控除額を詳細に入力できるものを選ぶことをおすすめします。
控除限度額シミュレーション事例
実際に年収一覧とシミュレーションサイトで計算した控除限度額の差は下記の通り。
【シミュレーション事例】
年収:400万
家族:配偶者(69歳以下)・子供(15歳以下)
iDeCo:24万円(年間)
生命保険料控除:4万円
上記事例では年収一覧で確認すると控除限度額は33,000円。
一方、シミュレーションサイトでiDeCo(小規模企業掛金控除)と生命保険料控除を入力して計算すると27,000円。控除額に6,000円の差が発生します。
上記の方が年収一覧でふるさと納税してしまうと、自己負担額が2,000円を超えてしまうことになります。
実際の控除額の確認方法
ふるさと納税した額が控除限度額内だったかを確認する方法はあるのでしょうか?
ふるさと納税は選んだ自治体に住民税を前払いし、翌年に居住自治体の住民税から控除してもらう制度。
よって、実際の控除額はふるさと納税をした翌年の5月か6月に居住自治体から送付される「住民税決定通知書」の"寄付金控除" あるいは "税額控除額"という欄で確認できます。


(出典:ふるさとチョイス)
上図は2万円をふるさと納税した事例ですが、摘要欄の市民税:10,800円と県民税:円7,200円と足すと18,000円となり、自己負担額が2,000円だったということが分かります。
シミュレーションした額と、実際の控除額が合わない場合は所得控除などの条件入力が誤っている可能性があります。
限度額を超えたら全額自己負担?|対処法は?

制度の仕組みがよく分からず、所得控除を考慮せずに年収一覧の限度額でふるさと納税をしてしまったという方もいるでしょう。
ふるさと納税が限度額を超えてしまった場合、超えた額は全額自己負担となってしまうのでしょうか?
実は、限度額を超えてしまっても全額自己負担となるわけではありません。
限度額をオーバーした分はふるさと納税の特例範囲外になりますが、「寄附金控除」 を活用することは可能。
例えば、控除限度額3万円の人が4万円分のふるさと納税を行った場合、自己負担金額は「2000円+超えた分1万円=1万2000円」よりも少なくなります。
ただし、「寄付金控除」を受けるにはワンストップ特例制度または確定申告で、オーバーした分も含めて全額を申請する必要があります。
よって、限度額を超えたとしても、ふるさと納税を行った金額をオーバー分も含めてしっかりと申請することが重要です。
寄付が限度額を超えた場合は確定申告
控除限度額の範囲内で寄付を行う場合、確定申告を行ってもワンストップ特例制度を利用しても、同じだけ税金の控除または還付が受けられます。
しかし、限度額の超過分については確定申告をする方が、自己負担金額が少なくなります。
これは、ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附金控除が「住民税から10%分」だけ。
一方、確定申告を行うと「住民税から10%分」の住民税控除に加え、「所得税から所得税率分(約5%-45%)」の所得税還付を受けられるから。
よって、控除限度額を超えて寄付を行った場合は確定申告を行うことをおすすめします。
なお、「控除限度額を1000円超えた際の自己負担分」については下表の通り。
| 課税所得 | 所得税率 | 確定申告 | ワンストップ 特例 |
|---|---|---|---|
| 〜194万9千円 | 5.105% | 849円 | 900円 |
| 195万〜329万9千円 | 10.210% | 798円 | 900円 |
| 330万〜694万9千円 | 20.420% | 696円 | 900円 |
| 695万〜899万9千円 | 23.483% | 665円 | 900円 |
| 900万〜1799万9千円 | 33.693% | 563円 | 900円 |
| 1800万円~3999万9千円 | 40.840% | 492円 | - |
| 4,000万円~ | 45.945% | 441円 | - |
早見表から分かることは控除限度額を少し超える程度であれば、大きな自己負担は発生しないということ。
よって、欲しい返礼品があるのであれば、限度額をちょっと超えて納税するというのも1つの考え方ではないでしょうか。
まとめ
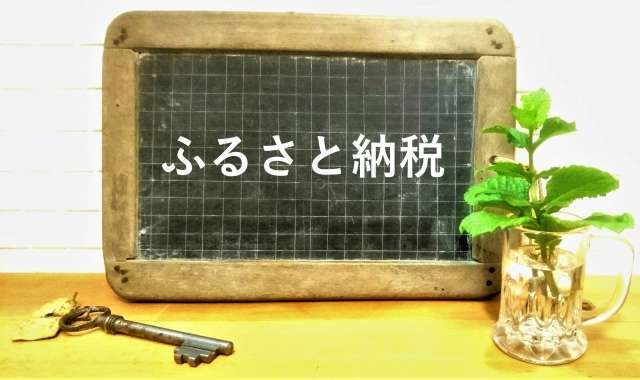
ふるさと納税をお得に利用するには、ある程度、制度の仕組みを理解する事が重要。
特に控除限度額は正確に把握する必要がありますので、安易に年収一覧を参考にするのではなく、シミュレーションサイトを利用する事をおすすめします。
また、仮に限度額を超えてふるさと納税を行ってしまった場合でも、ワンストップ特例制度か確定申告をすることにより超過額の全額自己負担を回避することが可能。
なお、控除限度額を超えてしまった場合は確定申告した方が自己負担額を少なくできます。
ワンストップ特例は無効になる可能性もあるので、シミュレーションのミスによる限度額超えが心配な方は、確定申告をしておいた方が安心でしょう。
なお、ふるさと納税については下記のような記事もありますので、参考にしてください。