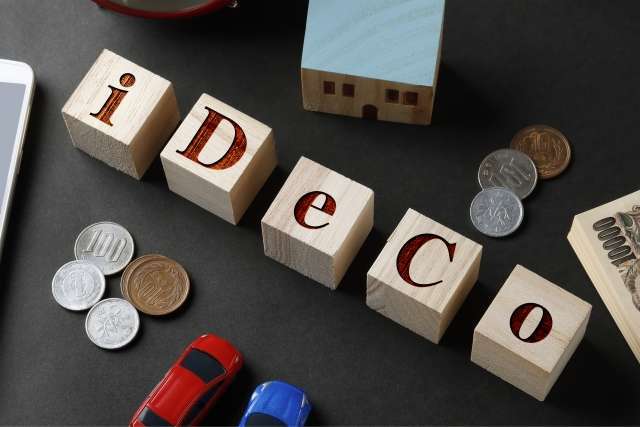
税制改正大綱が発表されてから「iDeCo改悪」が話題になりました。
今回の税制改正大綱ではiDeCo(イデコ)の掛金上限が引き上げられる案があり、喜んでいた方も多かったでしょう。
しかし、それと同時に出口は増税する改悪案が含まれています。
今回の改正案でiDeCoはどのように改悪される可能性があるのでしょうか?
今回の記事では、iDeCo改悪の内容について解説したいと思います。
財務省の暴走が許せない方は参考にしてください。
なお、2024年12月現在では改正案であり、まだ正式な法改正は行われていないのでご注意ください。
退職所得控除の5年ルールが10年ルールに変更
まずは簡単にiDeCoのメリットから解説します。
iDeCoのメリットは下記の通り。
- 掛金が全額所得控除
- 運用益が非課税
- 老齢給付の受取時にも税制優遇あり
iDeCo(イデコ)は掛金の全額が所得控除の対象となり所得税・住民税の負担を軽減でき、節税効果があります。
しかし、積み立てた資産を老齢給付金として受け取る際には非課税ではなく、元本部分も含めて課税の対象。
iDeCo(イデコ)の老齢給付金は、下記の受取方法を選択できます。
- 一時金
- 年金
- 一時金と年金の併用
一時金で受け取る場合も年金で受け取る場合も、どちらも課税の対象となります。
一時金で受け取る場合、受け取った一時金は退職金と同様に退職所得となり、所得税・住民税の課税対象。
ただし、退職所得には退職所得控除があり、受取額から下表の額を控除することができます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 ※80万円に満たない場合には、80万円 |
| 20年以上 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
※iDeCo(イデコ)は掛金の拠出期間を勤続年数とみなして計算
(参照:国税庁タックスアンサー「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」)
退職所得控除で注意すべきなのが、iDeCo(イデコ)の他に下記のような一時金を受け取るケース。
- サラリーマンが会社から退職金を受け取る場合
- フリーランス(個人事業主)が小規模企業共済を受け取る場合
iDeCo(イデコ)の一時金と同時に、サラリーマンが会社から退職金を受け取る場合や、フリーランス(自営業者)が小規模企業共済を一括で受け取る場合には、退職所得控除がiDeCo(イデコ)と同枠で計算されます。
しかし、iDeCo(イデコ)を一時金で受給後に5年以上経過してから退職金を受給すると、iDeCo(イデコ)の拠出期間分と退職金の勤続年数分の退職所得控除がフルに使用可能。
上記の「5年以上」という期間を「10年以上」に変更するというのが今回の改定案です。
現状は、iDeCoの一時金を60歳で受け取り65歳で退職金や小規模企業共済を受け取れば、退職所得控除をフルに使用可能。
仮に改正案が通ると、iDeCoの一時金を60歳で受け取った場合、退職金や小規模企業共済の受け取りを70歳までずらさないと退職所得控除をフルに活用できなくなります。
改正の理由は?
iDeCoの一時金より先に退職金や小規模企業共済を受け取る場合には、退職金の受け取りから20年経過しないと退職所得控除を満額利用できない「19年ルール」が存在します。
iDeCoの受け取り方によって「19年ルール」と「5年ルール」の両方が存在するのは不公平との指摘があったとのこと。
財務省は5年ルールの見直しでこうした不公平感を是正する狙いがあるとしています。
不公平という指摘があれば、なぜ「5年ルール」に統一しないのでしょうか。
制度改正する際には、必ず国民が不利になる方に統一されているイメージがあります。
私には財務省が増税したいだけとしか思えません。
掛け金上限を引き上げて出口で増税
先述の通り、今回の税制改正では下図のようなiDeCoの掛金上限を引き上げる改正案も出されています。

(出典:日本経済新聞)
入口は節税額を増やすような改正を入れておいて、同じ改正案の中にシレっと出口で増税となる改正案を仕込む。
今回の改正案が通った場合、iDeCoの受け取りは先になるので気付かずに増税になる人が増えるでしょう。
セコい手口で国家的詐欺といっても過言ではありません。
また、今回の税制改正では見送られましたが退職所得控除の縮小も議論されています。
来年以降の税制改正では、転職による円滑な労働移動を阻害しているという意味不明な理由で退職所得控除が縮小される可能性が高いでしょう。
今後も財務省主導で税制が決まる限り更なる改悪が待ち受けていると考える方が無難です。
5年ルールから10年ルールへの改正で影響を受ける人とは?
今回の税制改正で大きな影響を受けるのは下記のような人。
- 勤務先から退職金を受け取る人
- 自営業で小規模企業共済に加入している人
自営業で小規模企業共済に加入している人に関しては、ある程度は自身で小規模企業共済の受け取りをコントロールできるので、勤務先に退職金制度があるサラリーマンよりは影響が小さいといえるでしょう。
上記の方たちでもiDeCoが出口で増税されるのであれば、掛金を拠出する意味がないと判断するのは早計です。
収入が多い現役時代に所得控除を最大限使って課税を繰り延べし、収入が下がって税率が低い時にiDeCoや退職金などの税金を払うようにすれば一定の節税効果はあります。
なお、今回の改正案で影響を受けないのは退職金制度のない企業に勤めているサラリーマン。
しかし、そのような方も注意が必要。
先述の通り、退職所得控除の縮小が議論されていますし、財務省が力を持っている限り増税路線で制度改悪されることを想定しておいた方がいいでしょう。
まとめ

今回の改正案が通ると、iDeCoの掛金上限を引き上げることにより節税効果を上げておいて、出口で課税するという国家詐欺的な税制になります。
公的年金はマクロ経済スライドの導入により、実質的に受給額は減っていくことになります。
そうなれば老後資金は不足するからiDeCoやNISAなどで補えというのが国(政府)の方針のはず。
その老後資金の足しにするiDeCo受取時の税金を増やすような改正をする必要があるのでしょうか?
今回の「5年ルール」の改正は、掛金拠出時の節税額を増やしたから出口で増税して少しでも入りを増やしたいというのが本音のように感じます。
財政均衡主義に凝り固まった財務省が考えそうなこと。
今回のような姑息な増税策を繰り返してきたから日本経済は30年間も停滞し続けてきました。
そろそろ、私たち国民が目を覚まし財務省の暴走を止めなければなりません。